おもしろなのか、シリアスなのか
ykpythemind こんにちは。in-factoです。俺たちってなんかあれだよな。会話うまくできないよね。そういえば僕らがいつもしてるのは会話ではなくて会話のような音ゲーっていう話があった。
藤本薪 音ゲーすら出来てないっすね。
ykpythemind いつもと同じ感じで始まるのもあれだなと思って、別のことを言ってみたくなったんだけど。やったことないから。ポッドキャスト的なね。
藤本薪 ひとくだりみたいなのが。
トモヒロツジ 「はじまりました、革命チャンネル」
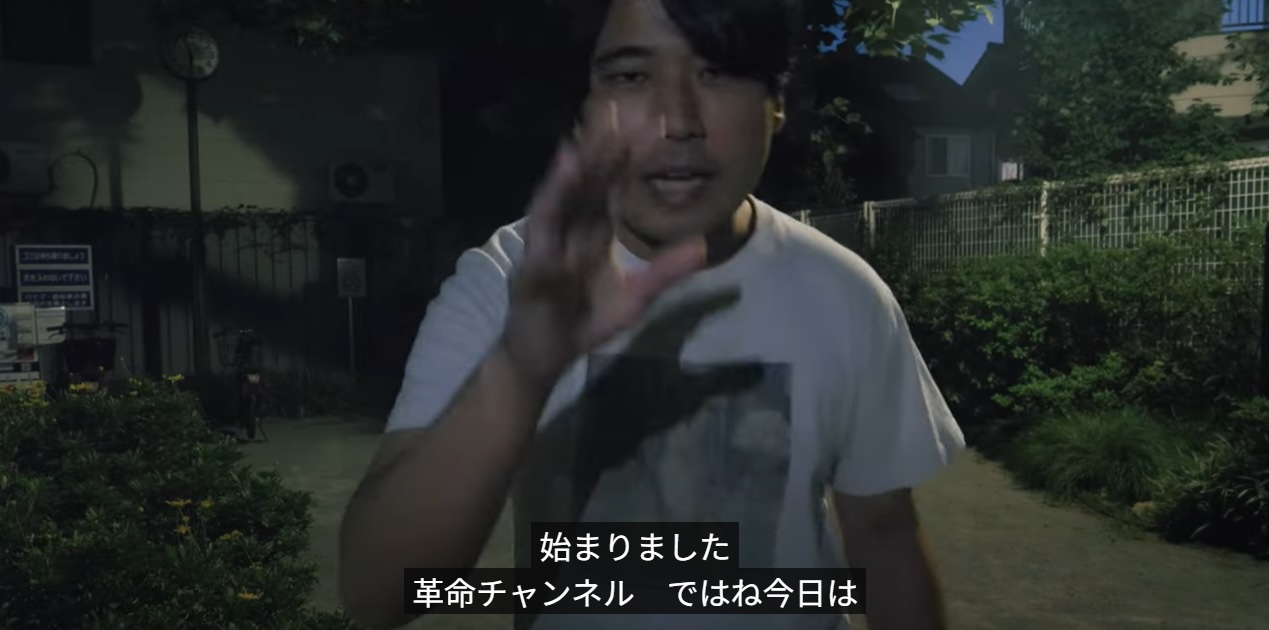
ykpythemind 今回の映像(プレゼント)、やっぱりシリアスにはなり切らなかったな。最近世に出てるホラーはそのシリアスさをやり切ってるのも多い中、俺たちそういうのできないよなっていう。
藤本薪 たしかに今回の映像もインタビューパートとかは割と安心して見れる感じというか。シリアスではあるけど、緩急ある。
トモヒロツジ 俺らって自分たちのこと俯瞰で見すぎてるんじゃない。シリアスにやってる自分に耐えられなくなるから、そういうの入れる。
ykpythemind ああ、それはあるね。
藤本薪 どうなんだろうね。ホラー作ってる他の人たちも、案外現場でゲラゲラ笑いながら作ったりしてんのかな。
ykpythemind いや、してないんだって(笑)
藤本薪 『呪怨』かな。「いや、こんな白い子供いないだろう。ぎゃはは」って笑いながら作ってたって話を聞いたことある。
トモヒロツジ ホラーってコメディでもあるからな。
ykpythemind コメディ要素を、見てる人の誰も求めてないんですよ(笑)
藤本薪 ホラーとコメディのどちらにも共通してるのは、不条理であるところだと思う。正しく正しいことが起きない、間違ったことが起きるっていうのは、やっぱりお笑いにもホラーにも共通するところで。ってなると、間違えるっていう現象自体に面白味があるというのもわかる。
トモヒロツジ でも、そういう瞬間にどこまでアドレナリン出るかは人によって違うのかもな、とかは思う。
ykpythemind そうね。なんか最近はコメディと感じられる要素は求められてない傾向にあるのかも。今回の『プレゼント』の話に入っていくけど、最後の展開を元々考えてたものから完全に変えてて。話の順序を逆転させる感じになったじゃないですか。あの風船作るシーンの絵が最後になることで、喜劇(コメディ)としてのエッセンスが出てきたなっていう。それを意図してたからいいんだけど。
トモヒロツジ そういう意味で言うと、あれ(風船を作るシーン)を最後に持ってこれるのが俺らしかできない感覚なんだと思う時は結構ある。やや言い過ぎかもしれないけど。映像を勉強して映像作家やってる人とは、バイオリズムが違うんだと思ってて。そこが奏功してるような感じはするけどな、俺は。
藤本薪 プロットを作ってる段階は時系列順だったじゃん(風船を作る→風船が家族の手に渡る)。それをひっくり返すことで、なんかハマったなって思ったのはあったよね。映像としての現実離れ度がだんだんと上がっていく形になるから、それはすごく美しいのかなと思った。みんなと同じ日常の地平から始めて、全然違うとこまで行くっていうことが。
ykpythemind 確かにね。
osd 脚本考えてる時は、藤本さんが結構時系列順を推してたというか。
藤本薪 うん。言ってたかも。そもそも僕は、ファウンドフッテージのお作法的に風船を作るパートを入れない方がいいと思ってたんだけど…。でも、結果としてよくなったと思う。
伏線回収アンチと疎結合ラバー
トモヒロツジ いろんなシーンがあるときに、シーン間のノリ付けをがっつりやらないのが自分らの作り方だなって思うことがあって。いろんな映像パーツをモジュールで見て、そのモジュール間の結合を割と疎にしてるから、並び替えが効くし、むしろ並び替えのプロセスで面白くできる余地を残すような作り方をしてるようなイメージがあって。見てる人が脳内で保管できないと、どっかで置いてかれるんだとは思うんだけど、そこは見てる側との一体感を信頼してる。
ykpythemind そう、でも一番簡単な部類の疎の作り方をしてる感じがする。そんなに言うほどできてないよねという意味で。
トモヒロツジ 結合を密にして、こちらが意図したカタルシスに導くみたいなの、俺あんま好きじゃなくて。途中から、レール敷かれてるなって感じがする時があるんだよね。結構伏線回収アンチなところがあって、パーツいっぱい並べて終わりに向けて編み上げるみたいなのがハマらない気持ちがある。
藤本薪 伏線回収や視聴者の誘導ができてない作品って、一般的には良くない作品になるんじゃないの。
ykpythemind 俺も割と良くない作品にありがちな気がする。商業的にはプロフェッショナルではないよね、とは思う。
osd 今回作るにあたって神視点というか、視点の話が制作の段階で議論されていたような気がしてて。伏線の見え方みたいな話で言うと、そこにある物語の中に作者(in-facto)の意図とか、手が加わった跡みたいなのが見えるのが嫌みたいな、そういう話なのかなと思いました。
ykpythemind 今回の『プレゼント』における、「この映像は、誰がどういう目的を持って編集したのか」みたいな背景の話だね。今回はそこに対して藤本くんがこだわり強かったな。テレビ局の人が編集したとかじゃなくて神の見えざる力が働いたかのように理不尽で脈略の無いカットの繋げ方をすると、逆に作り手の意図が透けるようになってしまって微妙なのでは?みたいな話も出てて。
藤本薪 ツジ君の言ってる「作者の意図が見える」みたいなことって、メタルギアやってて、最後に肉弾戦のシーンが入ると、「うわ、また小島秀夫のやつだ。」ってなるのが萎えるみたいなこと?。
トモヒロツジ 俺は小島秀夫のこと好きだから、逆にあれは「小島秀夫節」ねっていう喜びはあるんだけど…。

ykpythemind 結局ツジもその作品が好きかどうかで、予定調和を甘んじて受け入れるかどうかが決まっているってことなんじゃない。
トモヒロツジ それはある…。ただ初見で見るものに対して道筋が引かれすぎてると、なんか道筋があるなって感じがするから、なんかそういう人に向けることを考えると、あんまり明確にしたくないなとかはあるかもしれない。フラットに見られるものにしたいというか。
藤本薪 むしろ、ツジくんみたいなって人が増えてきたことによって、ドラマとか映画みたいな、監督がいて作ってるものとは別に、いわゆるファウンドフッテージみたいな拾ってきた映像を寄せ集めた形式の例えば『近畿地方のある場所について』みたいな、作品が流行ってるみたいなことかも。
ykpythemind 今のツジってもうマジョリティなんだ。
トモヒロツジ きびしい。
osd なんか個人的には、シンプルに「わかりやすすぎるとダメ」っていうだけの話な気もします。今までだったら、「フェイクドキュメンタリー」っていう構成自体が多少難解であるが故に、中身としては分かりやすくても受け入れられるものだったと思うんですけど。今はその構成自体が受け入れられてしまってるからこそ、中身の構成が多少わかりにくいもの、疎結合な作品が人気になってるというか、そういう話なのかなと思いました。
トモヒロツジ この話の初期のプロットって、インタビューパートが終わるところまでしか想定されてなかったんだよね。あの風船をどこからか持ってきて、その風船で一家に悲劇が起きる。で、「その風船がどうやってできてるか?」みたいなところって、書かない方がミステリアスなんじゃないかみたいな議論があったんだけど、ユキト(ykpythemind)が「ここはなんか足した方がいい」って話をしてたなと思ってて。それはフェイクドキュメンタリーが共通概念になったから一歩踏み込まなきゃということだったのかな、とosd君の話を聞いて思った。
osd ですね。最後に差し込まれる、風船を作る映像が入った結果バランス取れてるみたいな話もあるような気はしてます。
トモヒロツジ それと、あれが最初に出てくるか最後に出てくるかで、脱落する人の数が全然違いそうだなって思った。最初に出てくるには結構意味が分からない映像じゃん?(笑) あの映像が後になると、深堀りしたい人にとっては嬉しいし、別にインタビューパートで満足してる人にとってはそこで帰ってもいいし。
ykpythemind 確かに、ファンサービス的な。
藤本薪 確かにエンドロールの後に流れてそう。あとアニメで言うCパートみたいな?
osd 本当にエンドロールにしようっていう案もありましたしね。
トモヒロツジ そうね。その辺りの制作風景はYouTubeチャンネルでメンバー登録していただき、メンバーコンテンツを見ていただければ(笑)。
ykpythemind そう!今回からメンバーコンテンツがあります。
藤本薪 今後入るとどんないいことがあるんですか。
ykpythemind メンバーが本当にこの4人でホラー作ってるんだな、っていう風景が見られます。
トモヒロツジ どっちかというと、作り手側の気持ちが気になる人とかに向いてるコンテンツかもしれません。このテキストを毎回読んでくれてる方向けのコンテンツかも。基本的には映像を作ったタイミングでコンテンツも出すことになると思うので、コンスタントな更新を期待されてる方はお気を付けください。あくまで応援プランとして受け取っていただきたいです。
藤本薪 ホラーの世界観が好きな人とかはあんま見ない方がいいかも。
トモヒロツジ うん。世界観を好いてくれてる人はこんなネタバレテキスト読まないでください。
ykpythemind めちゃくちゃ突き放した。怖い。
藤本薪 では今回はそういう感じで終了します。
トモヒロツジ お疲れ様でした。
osd お疲れ様でした!
2025/09/23 収録
